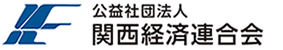NEWS FILE
2025年度
三重県企業ネットワークセミナーを開催

2月6日(金)、関経連エリアパートナーズ活動の一環として、三重県とともに、三重県企業ネットワークセミナーを大阪市内で開催した。
セミナーでは、一見勝之 三重県知事から同県における操業環境の魅力について紹介があった。続く基調講演では、田嶋徹 キンレイ常務取締役生産本部長兼生産部亀山工場長が、事業概要や2024年に亀山市に新設した工場の竣工までの取り組みについて説明した。
その後の交流会では、三重県産の食材を使った食事が振る舞われたほか、一部市町村関係者がブースを出展し、それぞれのまちの魅力を参加者にPRした。
「坐・三方よし」~マルチステークホルダー経営の実践に向けた企業の担当幹部の横のつながりの場~第5回会合を開催

2月3日(火)、企業制度委員会では「坐・三方よし」第5回会合を開催、会場・オンラインあわせて24社32名が参加した。
会合では、法政大学経営学部の北田皓嗣准教授がマルチステークホルダー経営やサステナビリティ戦略の実装に向け、組織行動を促す「社内浸透」のあり方について講演を行った。その後、同テーマに関するグループディスカッションを実施し、各社におけるマルチステークホルダー経営の浸透度合いや直面する課題を共有するとともに、他社事例をふまえた改善点などについて活発に意見を交わした。
続く交流会では、各社の取り組みなどについて、参加者間で積極的な情報交換が行われた。
リチャード・N・ラーセン 在大阪・神戸米国総領事との懇談

1月30日(金)、松本正義会長は、リチャード・N・ラーセン 在大阪・神戸米国総領事との懇談を実施した。
ラーセン総領事は、「関西は米国にとって重要な地域と認識している。着任して間もないが、関西地域の個性や歴史に裏打ちされた価値観に非常に感銘を受けた」と述べた。
これを受けて松本会長は、本年2月に実施予定の米国ビジネスラウンド・テーブル(BRT)等との意見交換や、3月に派遣予定の関経連米国・カナダ経済調査団など、関経連と米国とのかかわりについて紹介。両者は最近の国際情勢等についても意見を交わした。
さらに、トランプ大統領が2035年万博を米国に招致する意向を表明したことを受け、松本会長は「2025年大阪・関西万博で得た知見がある」と発言し、両者は今後も密接な連携を継続することを確認した。
第6回関西水素産業交流ラウンジを開催

1月27日(火)、水素にかかわる新たな出会いと交流を関西で創出するイベント「第6回関西水素産業交流ラウンジ」を近畿経済産業局とともに開催し、企業・団体・大学・自治体などからオンライン視聴を含め約150名が参加した。
当日は「~万博レガシーを活かす~水素等の社会実装に向けたシンポジウム」をテーマに、2025年大阪・関西万博で水素関連技術を披露した企業4社が登壇。万博会場内で水素を製造し、燃料電池を用いてパビリオンの電源の一部に使用した事例や、会場内で回収した生ごみからe-メタンを製造して供給するプロジェクトなど、先進的な取り組みが紹介された。
続く座談会では、技術の早期社会実装への期待や今後の課題などについて意見交換を行った。その後の名刺交換会では、参加者同士が積極的に交流を深めた。
けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会シンポジウム

1月26日(月)、けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会(事務局:当会、情報通信研究機構(NICT)、近畿総合通信局、関西文化学術研究都市推進機構)は、オープンラボシンポジウム2025を大阪市内で開催、小林充佳理事長(NTT西日本相談役、関経連副会長)が開会あいさつを行った。
シンポジウムには、高橋大輔 サントリー大阪工場技師長代理、土屋直樹 オムロン技術・知財本部デジタルソリューションセンタ長、板谷聡子 NICTダイバーシティ推進室長兼ネットワーク研究所ワイヤレスネットワーク研究センター研究マネージャーが登壇。スマートファクトリーやものづくりDXに関する事例紹介のほか、技術開発や実用化に向けた取り組みなどについてそれぞれ講演を行った。
その後、当協議会ワーキンググループの活動報告やポスターセッション等を通じて、研究内容や成果を紹介した。
APEC/ABAC 2025年大阪報告会を開催

1月26日(月)、ABAC*1日本支援協議会とともに「APEC*2/ABAC 2025年大阪報告会」をオンラインで開催した。
報告会では、外務省および経済産業省のAPEC高級実務者、APECの諮問委員会であるABAC日本委員から、APECのテーマ「Connect(連結)、Innovate(革新)、Prosper(繁栄)」、ABACのテーマ「Bridge(架け橋)」「Business(ビジネス)」「Beyond(未来に向けて)」に基づく2025年の活動内容について報告が行われた。
参加者からは、米国トランプ政権下における保護主義の台頭、強靭なグローバル・サプライチェーンの確保、2026年のAPEC議長国である中国との経済関係などについて質問が寄せられ、活発な質疑応答が行われた。
*1 ABAC:APEC Business Advisory Council(APECビジネス諮問委員会)。1996年設立のAPEC唯一の公式民間諮問団体であり、APECの政策に直接提言ができる。
*2 2025年の議長国は韓国
鳥取県×関西経済連合会 経済交流セミナーを開催

1月26日(月)、関経連エリアパートナーズ活動の一環として、鳥取県とともに経済交流セミナーを開催した。
セミナーでは、鳥取大学学長の原田省氏が「鳥取大学の挑戦」と題した基調講演を行った。原田氏は、鳥取砂丘を活用した国内唯一の乾燥地研究機関「鳥取大学乾燥地研究センター」や、地域課題の解決および学生へのアントレプレナーシップ教育等を担う「地域未来共創センター(愛称:Tottori uniQ)」など、具体的な取り組み事例を紹介。同大学の独自性や強みをPRするとともに、参加者に対して支援を呼びかけた。
続いて行われた交流会では、十河政則副会長によるあいさつの後、平井伸治 鳥取県知事が乾杯の発声を行い、参加者らは鳥取県産の食材を使った食事に舌鼓を打ちつつ交流を深めた。
地球環境・エネルギー委員会講演会

1月23日(金)、地球環境・エネルギー委員会では、早稲田大学研究院の遠藤典子教授を講師に迎え、「成長戦略としての原子力」と題した講演会を開催した。
講演では、国内外の原子力政策を取り巻く状況を概観するとともに、わが国の原子力をめぐる制度・事業環境上の課題について解説があったほか、今後講じるべき施策の方向性などに関して説明が行われた。
講師は、GX・DXの進展に伴い電力需要の増加が見込まれるなか、海外では原子力の活用が着実に進展している現状を指摘した。その上で、わが国においても原子力発電所の新増設を通じ、原子力発電関連技術・サプライチェーン、人材の維持・強化等をはかることが重要であると強調した。
都市OSワーキングイベント「防災DXピッチ&トークイベント」を開催

1月21日(水)、都市OSワーキングのイベントとして「防災DXピッチ&トークイベント」を開催、オンライン視聴を含め約70名が参加した。
冒頭、あいさつに立った小林充佳 副会長・DX委員長は、産学官が連携して防災DXに取り組む重要性を強調した。
続いて、スタートアップ4社による防災DXに関するピッチを実施。下條真司 都市OSワーキング座長および阿多信吾 プラットフォームサブワーキング座長からは、個別のソリューションにとどまらず、相互に連携しプラットフォームとして発展させていく必要性などについてコメントが寄せられた。
その後のネットワーキングでは、登壇したスタートアップと参加者との間での活発な意見交換が行われ、会場は大いに賑わった。
評議員会を開催
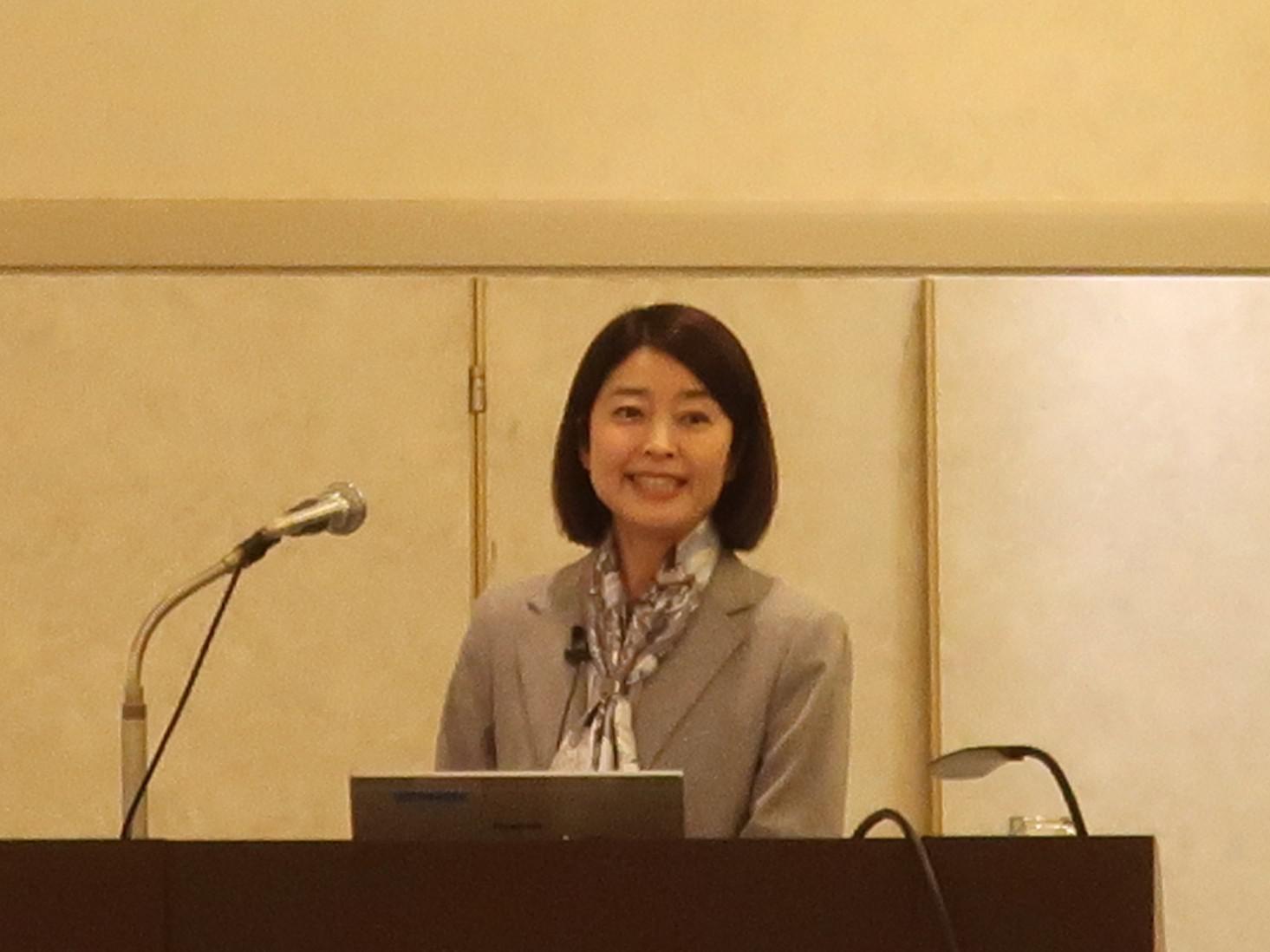
1月19日(月)、評議員会を開催、三菱総合研究所の武田洋子常務研究理事を講師に迎え、「2026年の世界・日本経済の展望~転換期の世界における日本の進路~」と題した講演をいただいた。
講師は、国際秩序、技術革新、資源・エネルギーの3つの地殻変動により世界は歴史的な転換期にあり、「ポスト・トランプ」でも保護主義・自国中心主義が続くという考えを示した。日本については、真に「強い経済」の実現に向けた分水嶺にあり、潜在成長力の強化と持続性の向上が求められると述べ、資源の成長分野へのシフト・新陳代謝、政策に対する市場からの信任確保が重要だと指摘した。
また、関西は2025年大阪・関西万博を契機にプレゼンスが向上していること、新しい技術・商品・サービスへの期待が高まっていること、海外企業等からビジネス連携の問い合わせが多数あることなどから、独創的な価値を創出し日本の変革を先駆ける年になると期待を述べた。